Thu
26
Apr
2018
先日の「忘れられた巨人」に引き続いて読んだ見たのがカズオ・イシグロ氏の長編デビュー作である本書「遠い山並みの光」です。ほとんど逆に辿って読み進めていましたが、ようやくデビュー作を読むことができました。イシグロ氏の出身である長崎と英国を舞台に、主人公の女性の回想にて語られるスタイルは、その後の作品の原型なのだなと改めて思わせます。戦後の復興期に生きた人々の苦悩がありつつも最後はどちらかというと希望(2人目の娘であるニキへの期待!?)の方に振れて終わる本書ですが、全体としてはやはり他の作品にも感じた一種の寂寥感が滲み出る作品かなと思います。
語られる回想自体は、主人公である佐知子が最初の子供を身ごもっている時に(この子供は長じて自殺してしまうのが冒頭で語られているのですが)、出会った母娘の描写を中心に戦後の長崎で大きなパラダイムシフトを経験せざるを得なかった日本の人々のストーリーが描かれています。その中で、全体を通じて佐知子自身の想いや考えは抽象的にしか語られないのですが、彼女が思いだしているそれらの回想シーンを通じて、彼女の現在の苦悩や過去の後悔が間接的に描写されているといった感じになっています。
話自体はそれらの回想の後に、現在のイギリスに戻って、唐突に終わりあっけない印象なのですが、この終わり方もつい先日に読んだばかりの最新作の「忘れられた巨人」に通じるものがあり、読後の読者の想像を掻き立てるように思えます。日本で出会った母娘の母である佐知子が分かっていながらもどうしてもアメリカに行くことにすがっていた描写と、それをある意味俯瞰してみていた主人公である悦子の対比は、やがて悦子自身が決して幸福な人生を歩まなかった(日本人の夫とは離婚して自身も英国に渡り、最初の娘の景子は自殺している現在形の描写がそれを物語っています)結末に収斂していきます。その現在形の悦子と、佐知子と出会った妊娠していた頃の悦子の心情の対比が交錯しながら物語は進むのですが、佐知子と悦子の立場が時間をずらしてオーバーラップしたような錯覚に陥って、最後はそれでも英国人との夫との二番目の娘であるニキへの希望で終わるところはカズオ・イシグロ氏の作風というかさすがという結末です。決して、主人公を美化せずに物語が終わるところは共通していますが、そんな殺伐とした無情な人生や世の中を描きつつ、きちんと「希望」を残すところが著作に共通している素晴らしい作風だとつくづく思います。
小説もSFも映画もジャンルを問わずですが、貴重な時間を割いて読んだり観たりする以上は、途中はともあれ結末に希望がない作品は読み手への裏切りにも等しいのではといつも感じています。そういった意味では、カズオ・イシグロ氏の作品はノーベル文学賞に相応しいものだと思わざるを得ません。引き続き、未読の作品を読んでみたいと思っています!








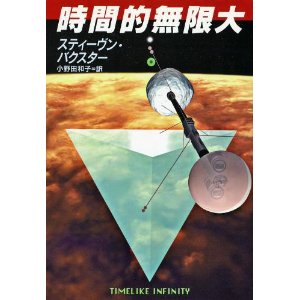






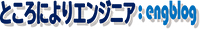
コメントはお気軽にどうぞ