Wed
19
Jan
2022
昨年のアウシュビッツの記憶もまだ覚めないうちにということで、アウシュビッツの体験談としては著名な「夜と霧」を遅ればせながら読了しました。題名の通り心理学者でもある著者のヴィクトール・E・フランクル氏が、戦中に強制収容に入れられた体験談ではあるのですが、全体を通して淡々と語られる収容所の内容もともかく、心理学者としての視点から収容者の感情や精神が蝕まれていく様子が、あくまで客観的に記述されている本著はある意味、別な形で現実感(もちろん本当の現実の出来事はるのですが)として伝わってきます。
本著での後半で、病気にかかった著者が病院へ移送される場面の下りは、本当に選択の残酷さを目の当たりにするところで、この収容所という局面が不条理に作られた環境という前提ではあるのですが、そんな中でも人の僅かな選択の違いで生死の運命が分かれてしまう恐怖が身に沁みます。
そして最後で解放された直後の描写に出てくる「離人症」という言葉も初めて知ったのですが、ネットで調べると下記のような症状とのことで、まさに収容所の生活が振り返れば悪夢でもない現実だったのか理解しがたい何かだったということなのでしょうか。
離人症とは、自分自身の意識(自我意識)や自己の感覚、または自己を取り巻く環境や物事について現実感が得られず、疎隔されていると感じる症状を指します。また、自分の意識が体から離れていったり、自分自身を客観的に観察したりするような状態に陥ることもあります。
具体的には、以下のような感覚が挙げられます。
- これまでの自分の感覚が普段と異なるように繰り返し感じる。
- 世界がぼやけてみえ、曖昧に夢を見ているかのように感じてしまう。
- 現実感を喪失し、その意味合いがわからなくなってしまう。
- 自分の身体の大きさや形が違って感じる。
- 見たことのない光景を見たことがあると感じたり(デジャヴ:既視感)、見たことがある光景を見たことがないと感じたりする(ジャメヴ:未視感)
など
また、「自分と世界の間にベールがあり世界がぼやけて感じる」と表現されることもあります。
※引用元サイトは下記になります。
最後のページの方にある下記の記述が、まさに収容所の日々の恐ろしさを物語っているとも言えます。
「そしていつか、解放された人びとが強制収容所のすべての体験を振り返り、奇妙な感覚に襲われる日がやってくる。収容所の日々が要請したあれらすべてのことに、どうして耐え忍ぶことができたのか、われながらさっぱりわからないのだ。(本著より引用)」
改めて思うのはやはり本当にこれが現実に行われたこととは思えない(ほどの)歴史的な人類史の事件であり、だからこそ絶え間なく伝え残していかなくてはならない内容であるということでしょうか。
本書自体は中編程度の内容ですぐに読めてしまいますが、面白いとかという以前の話として内容は本当に考えさせられる書籍だと思います。




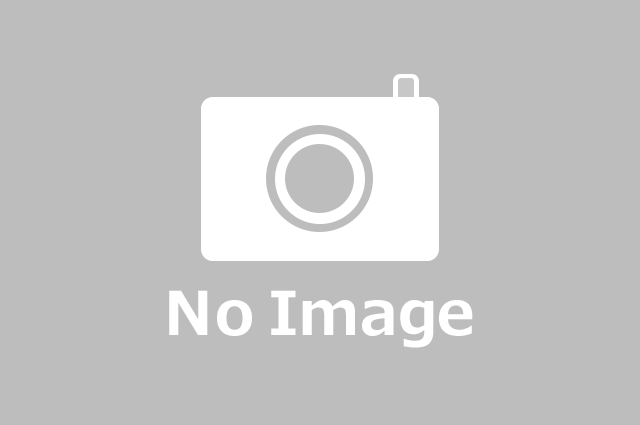











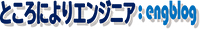
コメントはお気軽にどうぞ